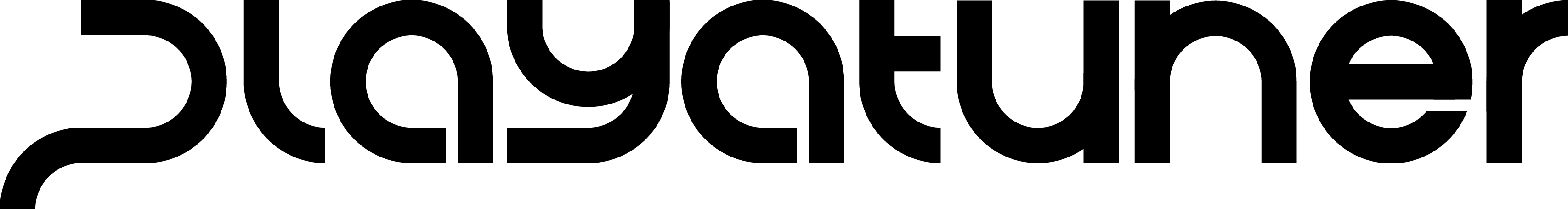QuestloveがD’Angelo「Voodoo」のドラミングを語ったインタビューをおさらいしよう
Writer: Akashi
D’Angelo(ディアンジェロ)の最高傑作「Voodoo」
96年中頃に始まった「Voodoo」の録音作業は、ブラックミュージック界でも多大なる信頼を獲得するQuestlove(クエストラブ)にとっても相当に過酷なものであったようだ。「Voodoo」にて披露されている「もたったドラミング」がいかにして生まれたかを、この映像でクエストラブが実演を交えながら語っているので是非おさらいしたいと思う。
クエストラブは、そのあまりの独特さに当初は他のミュージシャンに笑われるんじゃないか、と危惧したそう。しかしディアンジェロが「俺を信じろ、フォースを使え」と迫り続けたことから、あの独特のドラムスタイルに磨きをかけていったようだ(ちなみにクエストラブはスター・ウォーズを見たことがないらしい)。
それまでのドラムスタイルからの脱却にどれほどの時間を要したのか?という質問に対してクエストラブはこう語っている。
「96年から99年は人生で最もスタジオのドラムセットでドラムを叩いていた期間だったと思う」
その三年間はディアンジェロだけでなく、コモンの「Like Water For Chocolate」の制作やBilal、Erykah Baduなどといった面々と共に日々スタジオに入り、その中で徐々に自身のドラミングを進化させていったようだ。同時進行でこの面々が同じレコーディングスタジオにいることが凄い。
ディアンジェロのこの「もたったビート感」はBrown Sugarに収録されている“Me and Those Dreamin’ Eyes of Mine”にて既に発現していたそうだ。そのビートにクエストラブは疑問を持っていたようだが、ディアンジェロは「DAWのマニュアルを読んでいなかったんだ(笑)」という理由からこうしたビートが生まれたと語っている。だがそこに何かしらの味を制作チームが感じ取ったことから、そのビート感が採用されるという何とも不思議な偶然が働いたのである。ディアンジェロはクオンタイズをかけない実験的なビートへの拘りを強めるようになる。
さらに「ディアンジェロがJ Dillaから影響されたのか?」という質問に対してクエストラブは「ディアンジェロはJ Dillaと同時に、独自にこのビート感を生み出した」と解答している。
あの名作にまさかこんな裏話があったとは、と思うと同時にそうした自由度の高さが、ディアンジェロ作品に溢れる独特の人間味とグルーヴに繋がっているんだな、と妙に納得させられるインタビューでもあった。是非チェックして頂きたい。
いいね!して、ちょっと「濃い」
ヒップホップ記事をチェック!